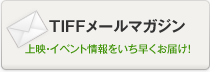2010.02.18
[更新/お知らせ]
<第4回映画批評家プロジェクト 結果発表>
<第4回映画批評家プロジェクト 結果発表>
第4回映画批評家プロジェクトの受賞作品が決定いたしました。
今回は前回を上回る、大勢の皆様からの応募をいただき、大変ありがとうございました。皆様からの映画に対する情熱を強く感じました。皆様への感謝の気持ちと共に、このプロジェクトをより意義のあるものにするべく、今後も取り組みを行ってまいります。
受賞された方はもちろん、惜しくも受賞を逃された方にも、またぜひ次回もチャレンジして頂ければと思います。
今回は審査の結果、佳作3名を選出いたしました。
今後の皆様のご活躍を願うと共に、応募して下さいました皆様に心より感謝いたします。
東京国際映画祭事務局 映画批評家プロジェクト一同
<第22回東京国際映画祭 映画批評家プロジェクト>
審査委員: 品田雄吉、土屋好生、明智惠子(キネマ旬報編集長)
表彰式の模様はコチラから
<第4回映画批評家プロジェクト 結果発表>
佳作:
藤澤貞彦 Sadahiko Fukazawa 『イースタン・プレイ』
深谷直子 Naoko Fukaya 『エイト・タイムズ・アップ』
古川 徹 Toru Furukawa 『ストーリーズ』
※クリックすると、各受賞作をお読みいただけます。これから作品をご覧になる方は、内容に触れている箇所がありますのでご注意ください。
※受賞者アイウエオ順
◆佳作
『イースタン・プレイ』 藤澤貞彦
無機質で、殺風景な団地の群れに朝日があたる。その前方に広がる荒地の前に兄弟が佇む。ここに高層ビルの群れが建つという。「ぼくらが慣れ親しんだこの風景も、もうなくなっちゃうんだ」子供の時分から何度ふたりでこの風景を見つめ続けてきたのだろう。ブルガリアは21世紀に入り、待望のEU加盟を果たしたとはいうものの、一方で貧困と失業が大きな問題となっている。彼ら取り残された人たちにとって、街の発展は豊かになることではなく、単に親しんだ風景を失くすことを意味しているに過ぎない。この作品は、全編そうした彼らの閉塞感で満たされている。しかしながら、ここから抜け出すための兄弟のベクトルは逆方向へ向いている。人は行き場所を見失ってしまった時、暴力に向かうことがあるのだが、弟は外に、兄は内へと向かっている。弟は、継母と怒りっぽい父親と暮らす家、この愛のない家で単に子供っぽい反抗を試みるのが精一杯だ。家の食べ物の「味が薄い」と感じるのは、舌が合わないということであり、彼の居場所がそこにないことを意味している。そして自分自身を肯定できないまま、人に引きずられネオナチ集団に入ってしまう。一方、画家でありながらドラッグ中毒治療中で、つまらない仕事に出る以外は、酒に溺れる日々を送る兄は、自分自身を否定し恋人をも冷たく突き放す。彼女と洒落たレストランで夕食を共にしても、ひとり「味が薄い」と感じている。そのことは、もはやふたりで共有できるものが何もないことを意味すると、繊細な彼は気がついている。
そんな兄弟が久しぶりに再会したのは、皮肉にもあるトルコ人家族を通じてである。弟は彼らを襲ったネオナチ集団のひとり。偶然通りかかった兄は、そこに弟がいるとも知らず、彼らを救おうとして逆に殴り倒される。今ブルガリアでは、反トルコ人感情が高まり、こうした事件が後を絶たないという。かつてオスマン帝国に500年近くもの長きにわたり直接統治されていたブルガリアが独立したのは、19世紀後半になってから。根強く残る反トルコ人感情が、フラストレーションが溜まった人々の間に噴き出してくるのも無理はない。そのことに気が付かず、のんびり街を楽しんでいたトルコ人の旅行者は、やはりかつての支配者側の人間なのだ。ネオナチ集団がそんな彼らを襲ったこと、ここに他のヨーロッパとは違うブルガリアならではの、トルコ人への複雑な感情がにじみ出ている。
しかしながら、兄弟のこの偶然の再会は、そんな状況を僅かずつではあるが変えていくことになる。それは兄の弟への愛である。家からもネオナチ集団からも抜け出せなかった弟は、事件後、兄から温かい言葉をかけてもらったことによって転機を迎える。一方、兄自身も事件で知り合ったトルコ人少女へ愛を見出すことによって、生きる力を取り戻していく。そのトルコ人少女が、どこか自分を別の世界へ連れて行ってくれる、そんな期待を持ったのかもしれない。暴力は、自分自身を傷つけていくことに過ぎず、深みにはまっていくばかり。一方愛は、勇気を与えてくれる。ネオナチから脱退する弟の勇気、酒浸りになるのをやめ、再び生きはじめる兄の勇気。ラストたどり着いたイスタンブール、ボスフォラス海峡の景色の何と明るいこと。そこに確かに希望が感じられる。ブルガリアの人々が抱える現代の閉塞感、これを打破するのにトルコ人に敵対していてはいけない。それは為政者たちのスケープゴートの罠に陥ることを意味する。こんな今だからこそ人々の友愛の気持が大切、兄弟の物語を通じそんな願いが作品に込められているようだ。
◆佳作
『エイト・タイムズ・アップ』 深谷直子
フランス映画らしく小洒落たアニメーション仕立てのオープニングに続くのは、若い女性が就職のための面接を受けているシーン。英語力が必須の外資系の会社で、当然彼女の履歴書にも英会話が得意、と書いてあるらしい。だが面接官から英語で質問を受けると、聡明そうな美人はみるみる半べそ顔になり、しどろもどろで言い訳をし始める……。できもしないのに大風呂敷を広げ、それが露見したときの顔から火が出るような恥ずかしい思いはきっと誰にもあるもの。身につまされながら、ああ、愚かしいなあ……、と、キュートな主人公の軽率さを笑う。
ここまでのテンポよい展開に、この作品を若いから許される猛進型女のコを描いたコメディかな、と思って見ていくと、徐々に明らかになる彼女の切羽詰った状況に驚かされることになる。離婚していて息子の親権も元夫に取られ、ひとり暮らし中。資格がないため定職に就けず、パートの仕事を掛け持ちしてなんとか食いつないでいる。だが家賃の滞納でアパートもいよいよ追い出されそう……。快活そうに見えながらも、実は人と交わることが苦手でこらえ性もない、ダメな三十路女性だった。
しかしそうと分っても彼女エルザはどこか魅惑的だ。めまぐるしい社会に適応できず、半分宙に浮いたような状態ながら、凛とした自分を持っている。世界的な経済恐慌で、どうしたってこぼれ落ちる人はいる。でもそれで崩壊してはいけないのだ。頭を低くしてやり過ごしながら、自らと向かい合っていくことが大事なのだ。
似たような境遇の隣人マチューとの交流も、彼女に変化をもたらしていく。マチューと出会ったばかりのころ、元夫の家でのディナーに招かれた彼女は、彼にエスコートを頼んで出かけた。だが単にひとりで行って恥をかきたくないという打算的な気持からだった。元夫とふたりになるとマチューを恥じるようなことを言い、一方でマチューに対しては夫のつまらなさを詫びる。だが男性たちは互いを気に入っていたようであり、エルザのコミュニケーション力の薄さが際立つシーンだった。
だが境遇がハードになるほどに、彼女は少しずつ成長していく。密入国者の仕事仲間が倒れれば、なんとか救おうとするし、自意識過剰のあまり撥ねつけてしまっていたマチューと、家を失った者同士森の中で穏やかな時を過ごすさまは美しい。圧巻は息子との海での出来事だ。どうしても手に入れたかった仕事の口を断られ落ち込む彼女は、母を励まそうと海からボール投げに誘う息子を疎ましがり、あらぬ方向に投げ返して、危うく彼を溺れさせそうになる。だがそこで、我に返り、救い出した息子を力いっぱい抱きしめるのだ……。彼女の殻が破れた瞬間。奇跡に立ち会った、と思うほど、生々しい激情の迸りがあった。
この作品のタイトルは、日本のことわざ、「七転び八起き」から取ったという。本当にエルザは落ちて落ちて、どん底を見た。でも起きるときには少しずつ前進しているというのが、見る人を励ましてくれる。ラストシーンで彼女は仕事を得ているけど、きっとすぐに失うだろうことも予感させる。それでも彼女の表情は今までにはない晴れやかさだ。仕事に就ける自信、人を愛せる自信を得たから……。
エルザを演じたジュリー・ガイエが素晴らしかった。水のようにしなやかな、不思議な存在感を放っていた。低い方へ低い方へサラサラ流れても、毅然とした透明感に満ちている。彼女なくしてこの作品はなかったであろう。今作ではプロデューサー業も務めた彼女だが、この絶妙な現代的感覚が、これからのフランス映画をおもしろくしてくれそうな気がしている。
◆佳作
『ストーリーズ』 古川 徹
観る側にも痛みを共有させる映画である。映画が始まると、手持ちカメラによる映像の揺れに不安を駆り立てられる。フォーカスが多少ズレても、カメラは執拗なまでにクローズショットで被写体を追い続け、その内面に切り込む機会を窺う。役者とカメラの息詰まる駆け引きにより濃密な空気が漂う。
冒頭の場面で、心理療法の受診者ロサリオは、自らの人間関係をフィギアを用いて示し、同時に映画の人物相関図が観客に提示される。そしてロサリオが倦怠期を迎えた主婦であること、彼女が心理療法を受けなければならない理由が、死産によるトラウマにあることが端的に明かされる。心理療法のルールに従って死者のフィギアを倒すわずかなアクション、その指先からこぼれる心の痛みをカメラは逃さずに捉える。
手持ちカメラを駆使したストイックな映像表現は、かつてラース・フォン・トリアーが牽引したムーブメント「ドグマ95」の記憶を喚起する。やや時代錯誤の感も否めないが、硬質な映像で綴られる物語には、「ドグマ95」へのリスペクトやノスタルジーの類には留まらない気高さを感じる。特筆すべきは、劇中劇との多重構造により表現することへの独自のスタンスを提示している点である。
ロサリオは不安を吐き出すように小説を書いている。その作品が劇中劇としてモノクロ映像で綴られる。そこには実体のない恐怖に苛まれ不眠症に悩む彼女の不安が暗い影を落としているが、余白が大きく物語を構成するに不可欠な要素が欠落している。
しかし、自らの痛みと向き合い、不安を克服したロサリオが執筆する物語は秀逸である。あらすじは次の通りだ。身重の画家に、ある老婆が8歳の孫の肖像画を依頼する。しかし彼女の孫は父親と共に交通事故で既に他界していた。しかも孫の近影は残っておらず、38歳の父親の写真から30歳若返らせて孫の絵を描いて欲しいと無理難題を言う。途方に暮れる画家だったが、やがて想像力を駆使して38歳から数段階に分けて8歳まで肖像画を若返らせる作業に挑む。
このデッサンの場面が圧巻である。冒頭からスクリーンにネガティブな作用を及ぼした映像の揺れが、画家に正のエネルギーを吹き込むことにより躍動感に転調する。小気味よい編集と画面の揺れが刻むリズム感が、画家の高鳴る胸の鼓動と重なり、小説を書くロサリオ、映画の作り手、そして映画を観る自分自身の鼓動と共鳴する。
やがて画家はその豊かな想像力と情熱によって奇跡を産み出し、息子と孫を同時に失った老婆の心に一筋の光を灯す。絵を描くこと、小説を書くこと、映画を撮ること、総じて表現することは何と崇高な作業なのだろう。小説の主人公、それを書く映画の主人公、それを撮る映画作家、それぞれの表現することへの情熱が渾然一体となって心を激しく揺さぶる。
表現することによって他人を感動させるなど、人間の想像力が産み出した奇跡かもしれない。映画を撮ることも極めて崇高な作業であり、それ故に作り手の責任は重い。表現する者が「産みの苦しみ」を負わなければ、鑑賞する者に本当の感動は与えられない。本作のマリオ・イグレシアス監督は、想像力を駆使して真摯に映像表現と対峙し、画家が絵筆を揮うように、小説家がキーボードを叩くように、彼はフィルムを廻すことによって、観る者の心に一筋の光を灯した。
観る側に痛みを強いるだけでなく、再生の喜びをも共有させる映画である。