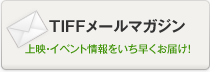2009.10.21
[インタビュー]
期待の新世代監督たち 3人に聞く【ロング・バージョン】 TIFF Times より
福島拓哉×松江哲明×石井裕也
TIFF Timesに連載され、好評を博した人気コーナー「期待の新世代監督たち 3人に聞く」。
紙面ではほんの一部しか伝えられなかった3人の対談を、公式サイトでは丸ごと紹介します!
これからの時代を担う若き監督たちの発言に要注目です!
福島拓哉 『OUR BRIEF ETERNITY』

1972年生まれ。『PRISM』(01・ソウル国際クィアフィルムフェスティバル)、『自由』(03・タイ短編映画祭)他。『東京失格』(06・井川広太郎監督)では俳優として主演を務める。
松江哲明 『ライブテープ』

1977年生まれ。『あんにょんキムチ』(00・山形国際ドキュメンタリー映画祭アジア千波万波特別賞、NETPAC特別賞受賞)。『あんにょん由美香』 (09)他。
石井裕也 『君と歩こう』

1983年生まれ。『剥き出しにっぽん』(05・PFFグランプリ)。『ばけもの模様』(07)他。エドワード・ヤン記念アジア新人監督大賞受賞(08・アジア・フィルム・アワード)。
――いまインディーズの定義が曖昧になってきています。インディーズというものをみなさんはどう考えますか?
石井 僕の中でインディーズと商業映画に明確な違いはない。インディーズという言葉が差別用語のように使われることがありますが、精神的に独立しているとか、そんなニュアンスならいいですけどね。そういう使われ方でない時が多いので、ちょっと言葉自体には嫌悪感がありますね。アングラをやろうとしているわけじゃないから、あまり意識してないんです。学生時代は奇をてらったりしましたが、それはメジャーを意識していて、同じ土俵では闘えないのがわかっていたからです。メジャーでも闘えるという自信がついてから、だんだん垣根をフェードアウトさせていきました。
松江 僕はすごく意識するんですよ。インディーズでしかできないことはなんだろうって。僕が作ってきたものがインディーズと受けとめられて、そのやり方で撮ってくれとメジャーから依頼されたこともあります。映画『デトロイトメタルシティ』のメイキングを作ったんですけど、その時、東宝からは『童貞をプロデュース。』のようにやってくれと言われた。『童貞をプロデュース。』はメジャーでできないものをめざした作品ですが、宣伝時にはアングラっぽく見えないように意識しました。
福島 日本にインディペンデントの概念が入ってきて、「自主制作」と翻訳されて、それが僕にはずっとミスリードだったような気がしてるんです。自主独立を指す言葉がいつの間にか、アマチュア映画のレッテルになってしまっている。スチューデント・フィルムとインディペンデント・フィルムがごっちゃになってるというか。後者は独立系プロの作品を指しますが、そういう言葉遣いじゃない場合が多いですよね。僕自身はインディペンデントをやりたいのではなくて、ただ映画が撮りたいだけなんです。でもメジャーな資本でやろうとすると、時間もかかるし、途中で立ち消えになってしまったりで、その結果インディペンデントになっている。今回の作品も出資を受けてますけど、間違いなくインディペンデントだと思います。
――松江監督の話では、インディーズの手法がメジャーに受け入れられる余地は十分あることになりますね。
松江 『ライブテープ』を撮った後、別のプロデューサーの人が、「メジャーでこのやり方をできないものか」と話していました(笑)。でもインディーズは手法としては語れないですね。手法じたいは、続けることによってある種のメジャー性を獲得することもありうる。インディーズの場合、その時々の責任を誰が負うのかが問題になる。僕は『ライブテープ』を前野健太という人でやりたかった。もし企画書を書いて出したら、前野さんじゃない人でと言われる可能性が出てきたり、道路許可の問題で誰か別の人が責任を負うわけです。でも自分でやる以上は、どんな状況になろうと自分で決めればいい。あと時間の問題もあります。企画書を出して通そうとすれば、1年はかかってしまう。あの映画は絶対に2009年1月1日に撮りたかった。だから、どうしてもインディーズでやらざるを得なかったんです。
――石井監督は今回商業映画第1作とのことですが。
石井 予算の250万円は、ある方がお詫びの印に出してくれたものです。以前1本映画を企画していて、それが頓挫してしまった。よくあることです。その方がスケジュールも空いてしまい申し訳ないと言って、ポケットマネーを出してくれた。はじめて予算をもらい、実験的なものをやるよりは、人を楽しませたほうがいいと思って、ああいう映画にしたんです(笑)
――なぜ駆け落ち話だったんですか。
石井 他にもいろいろ題材はあって、3個くらい出したけどダメだったんです。食肉偽装を暴く人……いますよね。あの話にしたんですけど、ダメと言われて。じゃあ、誰でも思いつくようなものをと。駆け落ちってあんまり最近はしないですけどね。
――石井さんの作品は非常にテンポがよくて、役者が丁々発止のやりとりを連発します。また脚本的には、時制が前後するうちに主人公たちの関係性が浮かび上がるという展開で、かなり技巧を凝らしています。
石井 俳優さんのほとんどが初めての人だったので、リハーサルをよくやりました。アドリブは一切ありません。基本的な脚本はありましたが、現場で台詞を作っていったんです。NGは結構出しましたね。時制については考えていましたが、3時間前の場面とか、最後の3年後の場面は最初頭になかったかな(笑)
――福島監督の『OUR BRIEF ETERNITY』はモノローグを用いて、主人公の内面を掬い取っていくような構成に特徴があります。
福島 モノローグやテロップはベタになってしまう場合が多いので、ふだんあまり使いませんが、今回入れてみたのは、映画全体のグルーヴを生みだしたいと思ったからです。音楽でいうベースラインみたいな感じで入れたわけです。こういうものをふんだんに加えて、映画全体を情報過多にするのが1つの目的でした。
――石井さんがお話的なよさを追求しているのに対し、福島さんはいま生きている人に届けたい気持ちが強いように思われます。
福島 ラブストーリーとパニックムービー的な仕掛けを用いて、「東京」という都市の概念を提示しようとしました。僕は埼玉出身ですが、地方に住んでいたこともあって、東京に対して主観と客観の両方ある。わかりやすく言うとすごく気持ち悪いんです。世界中のどの町よりも。だけど僕はここ以外には住めないなという気もしていて、それを表現したかった。今回、2人の作品を観たら、どちらも東京の話をやってる。これはなかなか大事かな。東京国際映画祭だから(笑)
――石井さんの作品はどこから東京に駆け落ちしてくる話ですか。
石井 要するに田舎なんですけど、僕は記号的に作っちゃってるんです。どちらかというと概念的なことなので。
――松江さんの吉祥寺はどうですか。
松江 あれは単純に、僕が吉祥寺で育ったからなんですよ。なぜ八幡神社から井の頭公園かというと、僕が子供のときに家族で行っていた道なんです。今年の元旦に撮りたかったのは、昨年死んだ父や祖母と一緒に廻ってた道だからです。あのルートを仲間たちと行きたかった。よく吉祥寺って映画に出てくるんですけど、すごい違和感があったんです。ヒラヒラした服を着た女の子が歩いてるみたいな(笑)。いねーよって思う。だから、それをちゃんと撮りたかった。道1本入ったら飲み屋があるとか、自販機があるとか。家族連れだったり、お爺ちゃんお婆ちゃんが一緒にいたりとか、もう本当に23区外なんですよ。みなさんのイメージする23区というのが多分わかりやすい東京なんです。でも僕はずっと外側に住んでいて、23区は都会って感じがする。その中途半端な位置が吉祥寺で、その辺をちゃんと撮りたいなというのはありました。
――吉祥寺八幡からバウスシアターに行って、バウスからサンロードを通ってハモニカ横町を抜けて、ロンロン、丸井前、井の頭公園の順ですね。
松江 本当は映画館の前に行きたかったんです。吉祥寺のTOWA会館。でもあそこは目の前に交番があるじゃないですか(笑)。撮影直前に警官が集まってきちゃった。あと井の頭公園にも警備員が集まってきて、「絶対やるな」と言ってきた。「絶対やるな」と言われてから、「ヨーイスタート!」って始めたんです。ほんとはこうしたトラブルをどんどん入れていこうと思ったけど、撮影の間にスタッフが警備員を説得してくれたんで、映画館は諦めたんです。
――福島監督は今回の映画を作るきっかけになったことはありますか。
福島 最大の要因はシネマアートン下北沢の閉館です。僕はシネキタを復館させたくていろいろ動いていたんです。でもうまくいかなくて、落ち込んだところで『イントゥ・ザ・ワイルド』を観て、すごく心に響いて、一念発起して映画を作ろうと思ったんです。
――ウィルスものという思い切った題材はどこから着想したのですか。
福島 岡崎京子の「リバースエッジ」という漫画が大好きで、あの中に出てくるウィリアム・ギブソンの詩からインスピレーションを得ています。「THE BELOVED」という詩なんですけど、久々にマンガを読み直したら、詩自体がすごく引っかかってきて。なかでも、「OUR BRIEF ETERNITY」(僕らの短い永遠)という言葉が一番気になった。そこから話を作っていきました。今回は記憶物ですけど、どうしてこういう題材になったかと言うと、その言葉からなんです。準備稿の段階ではもう少しわかりやすい話でしたけど、カラックスとかリンチが好きなので、無茶苦茶にしたかった(笑)。それでいろんな情報をバンバン入れて、それが映画全体のグルーブをつくるみたいな尖ったものにしたんです。
――みなさん映画を作るにあたって、これだけは譲れないというものはありますか。
石井 自分を誠実に出さなければならないということです。面白いと思っていることはちゃんと表現しないといけない。もう1つ、今これが正しいということをちゃんと考えなければならない。考えた上で、「俺はこう思う」ということを主張したいと思ってます。
松江 ドキュメンタリーは嘘をつかないと作れない。だから自分の中では嘘をつかないことですね。あとは作品に責任を持つということです。ドキュメンタリーは劇映画と比べて規模が小さいから、最終的に自分で責任を持たないといけない。
福島 映画的であることです。映画でしか表現できない映画の感情を見せたいんです。自分の映画を他のものに翻訳不可能なものにしたいんです。映画は総合芸術だから、映画でしか表現できないものを表現する。それが一番重要です。