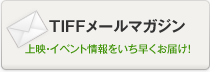2009.10.23
[インタビュー]
アジアの風部門『タレンタイム』:ピート・テオ(音楽)インタビュー

アジアの風部門上映作品『タレンタイム』(ヤスミン・アフマド監督)

ピート・テオ(音楽)さん
――ヤスミン監督との出会いと共同作業について教えてください。
僕は以前からブログを続けているのですが、2004年に「あなたの音楽が好きなんです」とヤスミンからメッセージが届いたんです。「今度『細い目』という映画を作ったので、スタジオまで見に来てくれないだろうか」と。それで会いに行き、いろいろ映画や音楽の話をして、とても気があったんです。それで『グブラ』(05)に楽曲を提供することになりました。それから、共同作業が始まり、ミュージックビデオやアースアワーという省エネのキャンペーンを一緒にやりました。といっても、僕が日本、韓国とツアーに行ったり、彼女も忙しかったりで、実際に会ったのは年に4回くらいでしたね。その代わり、携帯メールは毎日のようにしていましたけれど。
あるとき、僕が韓国のみでリリースした楽曲があると知った彼女が――「アイ・ゴー(I Go)」という曲なんですけど――次の映画で使いたいんだけどいいからしら、と言うんです。その作品が音楽劇ということもあって、最終的にはほぼ全楽曲を提供することになりました。
――『タレンタイム』ではその「アイ・ゴー」のほかに、「エンジェル(Angel)」「ジャスト・ワン・ボーイ(Just One Boy)」の2曲がメインの楽曲に使われています。使い方も巧みで、音楽に乗せられて最後まで一気に見てしまう。その構成は最初から構想されていたんですか?
美的な感性については僕と近いものがありましたから、『タレンタイム』では任された感じですね。脚本を読んで、このシーンでこういう曲がいいんじゃないかと提案していきました。ギターだけのアレンジだった「エンジェル」は彼女の希望でピアノにしたり、そういうやり取りはありましたけど、基本的には任せてもらいましたね。撮影前には全部の曲を作りました。俳優たちは口パクの練習をしないといけないので、撮影前に必要だったんです。
――映画のなかでピートさん自身の歌声は流れていましたか?
話し合いましたけど、僕のほうから、自分の声はないほうがいいと言ったんです。僕はもう中年ですから(笑)。声は多くを語ります。青春物なので、純真な感じを保ちたかった。
――ピートさんが作った曲はもちろん素晴らしいですけど、その他に挿入された楽曲もとても効果的でしたね。ドビュッシーの「月の光」やバッハの「ゴールドベルク変奏曲」といったクラシック、パキスタンの伝統音楽カッワリーの歌い手、ラーハット・ヌスラット・ファテ・アリ・ハーン(世界的名声を博したヌスラット・ファテ・アリ・ハーンの甥)の曲「O Re Piya」などが流れますが、その選曲もピートさんがなさったんですか?
僕とヤスミンで話し合って決めました。著作権の問題も発生しますから、その権利関係をクリアする仕事も僕が担当しました。
――ヤスミン監督はどんな音楽がお好きだったんですか?
彼女は音楽に精神性を求めていました。音楽を美しく、感情に訴えるものと考えていて、クールで精神的なものを伴わないものがかっこいいという現代の風潮からすると、古めかしい存在だったかもしれません。ただ、芸術的なものを創造するときに、笑いであれ涙であれ誰かの心に共鳴するものを求めているという点は僕も同じなので、彼女が好きなものは僕も好きでしたね。
――『タレンタイム』ではジョニー・キャッシュやニーナ・シモンの名前がセリフに出てきますが、ヤスミン監督が好きなんですか?
はい。余談ですが、沢田研二の『時のすぎゆくままに』を彼女に教えてあげたかったんです。絶対気に入ったと思います。美しいメロディ、メロディ自体に力あるものが彼女は好きでした。21世紀に入り、心に響くものより他の要素を重視している音楽が多いなかで、お互いそういうものにひかれていたんですね。
――ピートさんの音楽的な影響について教えてください。どんなアーティストがお好きだったんですか?
その話を始めると、時間がかかりますね(笑)。ベートーベン、ストランビンスキー、ジョニー・キャッシュ、ブルース・スプリングスティーン、レッド・ツェッペリン、エリック・クラプトン、テレサ・テン……中国の古典的な音楽やワールド・ミュージックと呼ばれるものも好きですね。日本人ですと、高田渡は素晴らしいと思いますし、最近は、Salle Gaveau(サル・ガヴォ)というバンドが大好きです。LSDでラリっているタンゴみたいなバンドなんですけど(笑)、とにかく気に入っていて、いつか一緒にやれたらいいなあと思っています。音楽的な部分で日本はいちばん進んでいるんじゃないですか。
――昨年、一昨年と日本でもライブ活動をされてますが、日本の観客についてはいかがですか?
とても怖いです(笑)。日本ではギターソロでのライブなので、場内が静かなんです。ミスがばれてしまう(笑)。
――日本人はミス云々じゃなくて、心に染みるように聴いていると思いますよ。
最初は勝手がわからなかったので静かな反応が怖かったんです。そのうち日本で演奏をするのが好きになりました。ここまで音楽に敬意を表して聴いてくれる観客はほかの国にはいない。だから、すごく練習して望みます(笑)。
――ピートさんはマレーシア新潮の中心的な存在でもありますね。「15マレーシア(15 Malaysia)」というピートさんがプロデュースした短編映画オムニバスのプロジェクトについてうかがいたいんですが、どういう趣旨で始めたんでしょうか?
発端は昨年ミュージックビデオの演出をヤスミン監督と、『心の魔』のホー・ユーハン監督にやってもらったんですが、そのときにマレーシアの政治や国民性が右派寄りになってきているという話になったんです。特にマレー系の人たちにそういう傾向が強くて、このままだとナチ化するんじゃないかと不安があって、立ち上げたプロジェクトです。50組120人のアーティストが有志で参加してくれて、すでに国民の2人に1人くらい聞いてくれていてとても評判がよかったので、また来年やってよといわれています。
なぜ短編映画だったかというと、マレーシアにはいい映画監督がいっぱいいますが、一般には知られていないから紹介したかったんです。短編であっても、ミュージックビデオよりは深く伝えられますしね。15作品集まりましたが、政治腐敗、幼児性愛、人種差別など、マレーシアが現在抱えている問題に向き合った作品が多かったですね。
メディアが政府傘下にあって検閲が厳しいので、インターネットを利用した方法であれば自分たちの表現ができるんです。これがテレビ映画でしたら検閲にあっていたでしょうね。ツーリズムの内容なら検閲しないけど、ほかのこととなるとすぐに問題視されてしまうんです。そのことに若い世代から不満が生まれていて、「15マレーシア」のウェブサイトを立ち上げたら45日で1000万のアクセスがありました。
あまりに人気があるので、僕が逮捕されると心配されたんですけど、逆にみんなに守られていると僕自身は感じていました。議論する場がやっとマレーシアに生まれつつあるのは感じています。
――『タレンタイム』では、主人公マヘシュのおじさんのガネーシ(インド系ヒンドゥー教徒)が隣家の人々(マレー系イスラム教徒)に殺されるエピソードが出てきます。異教徒同士が隣り合って暮らしていて、かたや結婚式、かたや喪中といった緊張した局面で起きる悲劇です。これは実際にあった事件ですか?
ええ、有名な事件でした。マレーシアは、いま、マレー系、中華系、インド系、この3つ政党がしのぎあっていますが、他の2つの政党から抜きんでるために相手を敵視する政策をとるんです。つまり人種、肌の色を持ち出すわけです。だからこそ、ヤスミンがマレーシアでいちばん重要な監督だったんです。私たちが将来進んでいくべきビジョンを示してくれた。宗教や肌の色を超えたものを提示してくれたんです。マレーシアで映画というと、マレー系映画と固定観念がありますが、その内容はどんどん右寄りになっています。東京や釜山でヤスミンの映画を見せると、なぜマレーシアで問題視されるのかわからないといわれるけど、マレーシアでは物議をかもし出しているのはそういう状況があるからなんです。中華系の女の子とマレー系の男の子が付き合っているだけで問題視されるんですよ。気楽に恋ができないなんて異常な世界ですよね。
――ヤスミンは人間の可能性を描いた素晴らしい映画作家でした。
じつは60年代や70年代初頭まではこういう問題はなかったんですね。連立政権が誕生し、政治のゲームから様々な問題が出てくるようになったのがこの30年なんです。そういう背景があるからこそ、若い人がヤスミンの映画を支持しているんです。
聞き手 赤塚成人