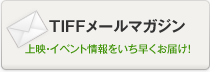2009.10.22
[インタビュー]
natural TIFF部門『石油プラットフォーム』:マルク・ヴォルフェンスバーガー監督、イザベラ・ガッティカー(プロデューサー)インタビュー
カスピ海に浮かぶ石油採掘のための人口都市「オイルロックス」
人々の目から隠されていたその存在を明らかにした
マルク・ヴォルフェンスバーガー監督が語る撮影の裏側
『石油プラットフォーム』

――はじめに、ヴォルフェンスバーグ監督の経歴を教えてください。
W(ヴォルフェンスバーガー) 大学では経済学をしました。何かを始める前に、まず世の中のシステムを知ることが必要だと思ったからです。卒業後、ヨーロッパ開発銀行でライターの仕事に就き、そこで中央アジアのことを知り関心をもつようになりました。退職後、中央アジアを専門領域としたジャーナリストの仕事を始めました。オイルロックスを見つけたのもそういう経験があったからこそなんです。1999年にその存在を知ったのですが、立ち入り許可もおりず本当に存在するのか確かめることができない。それでリサーチを何ヶ月もしているなかで、オイルロックスに水を供給しているボートをみつけたんです。必死で交渉したところ、1時間だけ滞在する許可を船長さんからもらいました。もちろん捕まれば船長も私も刑務所行き。船長にとってはすごいリスクだったでしょうね。足を踏み入れたオイルロックはとにかく驚くべき場所でした。これは正式に取材しようと決意したのですが、許可が下りない。2年後、スイスに戻り、ブルーバードというプレスエージェンシーに登録して仕事を始め、8年間はイランやアフガニスタンへ取材に行っていました。2006年からテレビの仕事を始め、その後、独立しようと思ったときに、まずオイルロックスのことを取材したいと思って、再び交渉を始めました。
――ガッティカーさんのプロフィールも教えていただけますか?
G(ガッティカー) ジェノバ大学で歴史を学び、パリでも勉強したあと、1993年からフィクションやドキュメンタリーをプロデュースするインターメッゾ(Intermezzo Films)という会社にプロデューサーとして入りました。
――映画はもともと好きだったんですか?
G フランス語圏のスイスでは様々な映画を製作する会社として有名で信頼できるところに惹かれました。アモス・ギタイのアシスタントコーディネーターとして、2年間イスラエルフィルムで仕事をしたこともとても勉強になっていますね。
――『石油プラットフォーム』撮影の苦労について教えてください。
W 製作費が確保できるかどうかわからなかったので、まず自分とカメラマンだけで撮影に行きました。カメラマンも自分でギャラを払ったんです(笑)
G その後、私たちの会社が入り、資金集めをして製作したので、そのカメラマンのギャラはうちから払いました(笑)。
W アゼルバイジャンは人口400万人の小さい国ですが、とても面白い場所です。石油とガスなど天然資源は豊富ですが、石油でお金をもうけているという事実は国の評判を落とすものとして隠している傾向があります。本来であれば誇りをもつべきですが、恥じている。ですから撮影にこぎつけるまでに大変な時間がかかりました。
何回話しても許可がおりなかったのですが、ようやく自然破壊がテーマではなくそこで暮らす人々の生活を撮ろうとしているんだと理解してくれたんです。またスイスの大統領と話す機会があったので相談したところ、アゼルバイジャンの大統領と話してくれて、それからスムーズに進むようになりました。ですから、交渉時間と撮影時間が逆転しているんです。1年交渉してやっとおりた撮影許可がたった2日間。それでは無理だと交渉して、1週間に伸ばしてもらったんですけど、撮影を開始したら、2日目には戻ってこいと、ヘリコプターを待機させているんです。断って撮影を続行しました。撮影中も常に内務省の人間が見張っていて、ソビエト支配時代に戻ったのかと錯覚するくらいでしたね。
そんな苦労を経て、ティーザーを作りスイステレビに持ち込んだところ、素晴らしい、大きなプロジェクトでやろうと言ってもらえたんですけど、そうなると素材が足りない。もう一回撮影に行く必要がありました。そこで石油会社の役員に映像を見せたのですが、彼らは批判するわけです。なぜ過去のオイルロックスを見せるんだ、現在のフィルムを見せろと。でも、彼らだって何年も現地に行っていなかったので、いまどういう状態なのかわかっていなんです。情報も隠されていたので、役員すら知らなかった。そんな誤解もあり、交渉は難航したのですが、最終的には1週間の撮影許可をくれました。
今度は平和な1週間でした。ただ、前回に撮影した人が誰もいなくなっていたので、ゼロからのスタートでしたね。また、アゼルバイジャンはシャイな人が多く、下手なことを言うとクビになると怖れているので、口から出てくるのはプロパガンダばかり。真実を話してくれる人を探すのが難しいんです。あなたのことは尊重します、決して馬鹿にはしません、そのまま映しますということを理解してもらうよう努めました。栄光と呼べるものではないかもしれないけど、隔離され、世界中が知らないところで誇りを失わず過酷な仕事をしている人々の様子を、世界中の皆さんに見せることができ、自分としてはうれしく感じています。
石油会社には長いバージョンを送っているんです。11月7日が設立60周年だそうです。オイルロックスにはいまは使用していない500人収容の映画館があるのですが、そこで上映してくれたら最高ですね(笑)。ただ誇りに思うと同時に国の恥という意識もあるので、アゼルバイジャンの政府としてその事実を公表するかどうかはわかりません。いま、交渉中です(笑)。
――交渉がなかなか進まないときに、途中で撮影を断念しようとは思いませんでしたか?
G この人にはそういう血は流れていないと思います(笑)。いい監督というのは絶対に諦めないですね。逆に諦めたらいい映画はできないと思います。
W ジャーナリストがいい記事を書かないとその場所の印象は悪くなり、結果的に書かれた人をすごく傷つけることになるんです。だから取材できるように説得するのは大変なんだけど、ここは素晴らしい場所だと信じることができれば、絶対に諦めないで交渉します。もちろん、真実を映せないと思ったらそのときは諦めますが。
――撮影中、オイルロックスの住み心地はいかがだったでしょうか?
W 国賓級のもてなしだったんですね。大きな食堂で食事を用意してくれたんですが、残念ながらそこで働いている人たちには値段が高すぎて、誰も食事に来ないんです。一般の人から隔離されてしまったところはあったと思います。ただ、ロシア語が話せることが役に立ちました。カメラマンとサウンドエンジニアが内務省の人間を連れ出している間に、直接私がロシア語で話しかけるんです。見張られていないとわかればみな正直に話してくれました。非常に過酷な場所なので、多くの人が亡くなっています。そういう人たちの犠牲の下にいまがあるという複雑な思いを持っている。みんな話したいんだけど、話せない。記録には残っていないそんな思いを伝えることができればと思いました。
――今後の活動を教えてください。
W 同じような手法を考えています。小さいストーリーから始めて、面白ければ大きくしていくやり方です。カザフスタンやウズベキスタンなど中央アジアにはまだまだ皆さんの目に触れてない場所がありますので、2010年には一人で戻って映画を撮ります。入るのが難しい国ほど交渉で闘わないといけないのですが、中毒みたいなもので無理だと言われるとどうしても入りたくなるんです(笑)。
G 自分も中央アジアに惹かれているので、彼のプロジェクトに興味をもっています。あの一帯はインド、パキスタン、トルコなどいろんな国の利権が入り込んでいて、翻弄されているので、そういう状況をもっと伝えていきたいと思いますね。
――その作品が東京で見られることを楽しみにしております。
G 2人とも日本は始めてですが、招待されて光栄ですし、皆さんに温かく出迎えていただいてとてもいい時間をすごしています。ぜひ、もう一度来日したいと思っています。
W この作品は島国の皆さんにはわかってもらえると彼女は言っていたんですよ。
G 日本も島国ですよね。だから今回日本で上映されたことは何かの縁だったと思います。
聞き手 武田俊彦
人々の目から隠されていたその存在を明らかにした
マルク・ヴォルフェンスバーガー監督が語る撮影の裏側
『石油プラットフォーム』

マルク・ヴォルフェンスバーガー監督、イザベラ・ガッティカーさん(プロデューサー)
――はじめに、ヴォルフェンスバーグ監督の経歴を教えてください。
W(ヴォルフェンスバーガー) 大学では経済学をしました。何かを始める前に、まず世の中のシステムを知ることが必要だと思ったからです。卒業後、ヨーロッパ開発銀行でライターの仕事に就き、そこで中央アジアのことを知り関心をもつようになりました。退職後、中央アジアを専門領域としたジャーナリストの仕事を始めました。オイルロックスを見つけたのもそういう経験があったからこそなんです。1999年にその存在を知ったのですが、立ち入り許可もおりず本当に存在するのか確かめることができない。それでリサーチを何ヶ月もしているなかで、オイルロックスに水を供給しているボートをみつけたんです。必死で交渉したところ、1時間だけ滞在する許可を船長さんからもらいました。もちろん捕まれば船長も私も刑務所行き。船長にとってはすごいリスクだったでしょうね。足を踏み入れたオイルロックはとにかく驚くべき場所でした。これは正式に取材しようと決意したのですが、許可が下りない。2年後、スイスに戻り、ブルーバードというプレスエージェンシーに登録して仕事を始め、8年間はイランやアフガニスタンへ取材に行っていました。2006年からテレビの仕事を始め、その後、独立しようと思ったときに、まずオイルロックスのことを取材したいと思って、再び交渉を始めました。
――ガッティカーさんのプロフィールも教えていただけますか?
G(ガッティカー) ジェノバ大学で歴史を学び、パリでも勉強したあと、1993年からフィクションやドキュメンタリーをプロデュースするインターメッゾ(Intermezzo Films)という会社にプロデューサーとして入りました。
――映画はもともと好きだったんですか?
G フランス語圏のスイスでは様々な映画を製作する会社として有名で信頼できるところに惹かれました。アモス・ギタイのアシスタントコーディネーターとして、2年間イスラエルフィルムで仕事をしたこともとても勉強になっていますね。
――『石油プラットフォーム』撮影の苦労について教えてください。
W 製作費が確保できるかどうかわからなかったので、まず自分とカメラマンだけで撮影に行きました。カメラマンも自分でギャラを払ったんです(笑)
G その後、私たちの会社が入り、資金集めをして製作したので、そのカメラマンのギャラはうちから払いました(笑)。
W アゼルバイジャンは人口400万人の小さい国ですが、とても面白い場所です。石油とガスなど天然資源は豊富ですが、石油でお金をもうけているという事実は国の評判を落とすものとして隠している傾向があります。本来であれば誇りをもつべきですが、恥じている。ですから撮影にこぎつけるまでに大変な時間がかかりました。
何回話しても許可がおりなかったのですが、ようやく自然破壊がテーマではなくそこで暮らす人々の生活を撮ろうとしているんだと理解してくれたんです。またスイスの大統領と話す機会があったので相談したところ、アゼルバイジャンの大統領と話してくれて、それからスムーズに進むようになりました。ですから、交渉時間と撮影時間が逆転しているんです。1年交渉してやっとおりた撮影許可がたった2日間。それでは無理だと交渉して、1週間に伸ばしてもらったんですけど、撮影を開始したら、2日目には戻ってこいと、ヘリコプターを待機させているんです。断って撮影を続行しました。撮影中も常に内務省の人間が見張っていて、ソビエト支配時代に戻ったのかと錯覚するくらいでしたね。
そんな苦労を経て、ティーザーを作りスイステレビに持ち込んだところ、素晴らしい、大きなプロジェクトでやろうと言ってもらえたんですけど、そうなると素材が足りない。もう一回撮影に行く必要がありました。そこで石油会社の役員に映像を見せたのですが、彼らは批判するわけです。なぜ過去のオイルロックスを見せるんだ、現在のフィルムを見せろと。でも、彼らだって何年も現地に行っていなかったので、いまどういう状態なのかわかっていなんです。情報も隠されていたので、役員すら知らなかった。そんな誤解もあり、交渉は難航したのですが、最終的には1週間の撮影許可をくれました。
今度は平和な1週間でした。ただ、前回に撮影した人が誰もいなくなっていたので、ゼロからのスタートでしたね。また、アゼルバイジャンはシャイな人が多く、下手なことを言うとクビになると怖れているので、口から出てくるのはプロパガンダばかり。真実を話してくれる人を探すのが難しいんです。あなたのことは尊重します、決して馬鹿にはしません、そのまま映しますということを理解してもらうよう努めました。栄光と呼べるものではないかもしれないけど、隔離され、世界中が知らないところで誇りを失わず過酷な仕事をしている人々の様子を、世界中の皆さんに見せることができ、自分としてはうれしく感じています。
石油会社には長いバージョンを送っているんです。11月7日が設立60周年だそうです。オイルロックスにはいまは使用していない500人収容の映画館があるのですが、そこで上映してくれたら最高ですね(笑)。ただ誇りに思うと同時に国の恥という意識もあるので、アゼルバイジャンの政府としてその事実を公表するかどうかはわかりません。いま、交渉中です(笑)。
――交渉がなかなか進まないときに、途中で撮影を断念しようとは思いませんでしたか?
G この人にはそういう血は流れていないと思います(笑)。いい監督というのは絶対に諦めないですね。逆に諦めたらいい映画はできないと思います。
W ジャーナリストがいい記事を書かないとその場所の印象は悪くなり、結果的に書かれた人をすごく傷つけることになるんです。だから取材できるように説得するのは大変なんだけど、ここは素晴らしい場所だと信じることができれば、絶対に諦めないで交渉します。もちろん、真実を映せないと思ったらそのときは諦めますが。
――撮影中、オイルロックスの住み心地はいかがだったでしょうか?
W 国賓級のもてなしだったんですね。大きな食堂で食事を用意してくれたんですが、残念ながらそこで働いている人たちには値段が高すぎて、誰も食事に来ないんです。一般の人から隔離されてしまったところはあったと思います。ただ、ロシア語が話せることが役に立ちました。カメラマンとサウンドエンジニアが内務省の人間を連れ出している間に、直接私がロシア語で話しかけるんです。見張られていないとわかればみな正直に話してくれました。非常に過酷な場所なので、多くの人が亡くなっています。そういう人たちの犠牲の下にいまがあるという複雑な思いを持っている。みんな話したいんだけど、話せない。記録には残っていないそんな思いを伝えることができればと思いました。
――今後の活動を教えてください。
W 同じような手法を考えています。小さいストーリーから始めて、面白ければ大きくしていくやり方です。カザフスタンやウズベキスタンなど中央アジアにはまだまだ皆さんの目に触れてない場所がありますので、2010年には一人で戻って映画を撮ります。入るのが難しい国ほど交渉で闘わないといけないのですが、中毒みたいなもので無理だと言われるとどうしても入りたくなるんです(笑)。
G 自分も中央アジアに惹かれているので、彼のプロジェクトに興味をもっています。あの一帯はインド、パキスタン、トルコなどいろんな国の利権が入り込んでいて、翻弄されているので、そういう状況をもっと伝えていきたいと思いますね。
――その作品が東京で見られることを楽しみにしております。
G 2人とも日本は始めてですが、招待されて光栄ですし、皆さんに温かく出迎えていただいてとてもいい時間をすごしています。ぜひ、もう一度来日したいと思っています。
W この作品は島国の皆さんにはわかってもらえると彼女は言っていたんですよ。
G 日本も島国ですよね。だから今回日本で上映されたことは何かの縁だったと思います。
聞き手 武田俊彦