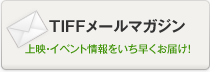2009.10.21
[インタビュー]
アジアの風部門『青い館』グレン・ゴーイ監督インタビュー

グレン・ゴーイ監督

――前作『フォーエバー・フィーバー』(98)から、今回のTIFFで上映された新作『青い館』(09)まで、約10年のブランクがありましたが、その間、どのような活動をされていたのでしょうか?
映画監督になる前からやっているのですが、その間は主に演劇の演出をしていました。映画は脚本作りと資金調達が大変ですが、表現に値するオリジナル脚本を作るのに時間がかかったんです。私は大学時代から約20年間ロンドンで暮らしていたのですが、『フォーエヴァー・フィーバー』はロンドン移住前、10代の総決算だと思って作りました。また、8年前にシンガポールに帰ってきて、自分の家族や友人と新たな環境を構築するのに時間がかかったのも原因です。
シンガポールではマスコミ媒体がすべて政府傘下にあり、企業といってもすべて国営。表現の自由が限られているんです。そんな環境を現実にどう反映できるか、考えて作ったのが『青い館』です。
――シンガポールの文化や個性を描きながら、物語や人物像が普遍的なところに達していて素晴らしいと思いました。
『青い館』では21世紀におけるアジアの家父長制を考察したかったんです。いままでは、社会秩序を守り、国の発展に貢献するために、家父長制が幅をきかせてきました。ただ、それによって個人の自由が犠牲になってきた面もあったと思います。特にアジアには個人の意見を出しにくい風土がありますから、『青い館』では国家を家族にたとえて作りました。シンガポールはアジアのなかでも非常に小さな国ですが、政府だけではなく家族、教育、宗教でも若い人を縛っています。個人を表現する空間が少ないんです。
――主役の大物実業家を演じたパトリック・タオがとても魅力的でした。
彼のバリトンボイスは素晴らしいですね。
――彼は独裁者的な存在ですが、最後は悲劇的な事実が判明する。でも、この映画の印象は明るい。それは圧制的な状況がなくなり個人が自由に生きていける社会を監督が願っていると解釈してよろしいでしょうか?
あなたの解釈は正しいです(笑)。でも、じつはもう少しひねっていて、親がいなくなって初めて自分の姿がわかるということはあると思います。親がなくなった時点で新しい人生、セカンドチャンスが始まるんだよと。私の場合がそうだったんですよね。また、私たちはうまくいかないと常に誰かの責任にしがちですけど、違うと思うんです。大人になったら自分の選択は誰のせいにもできないんだよと。
また、『青い館』のもうひとつの側面として、シンガポールの政治状況があります。シンガポールでは人民行動党(PAP)政権があるんですけど、50年近く変わっていない。日本では最近、政権が変わりましたけれど、シンガポールは変わらない。人民行動党が作ったシステムがあまりにうまくできているので、投票で異を唱えて変えようとは若い人も思えない。恐怖感があると同時に物質的なものは満たされている状況で、それを犠牲にしてまで声を出す勇気はあるのかということなんですよね。
――『青い館』というタイトルはどこからつけられたのですか?
マレーシアのペナンにある、1890年代に建てられたマンションで撮影したのですが、そこニックネームがblue mansion(青い館)だったので、そのままタイトルにしました。プロダクション・デザイナー(美術)の人から、テーマとなる色を尋ねられたときに、青とグレーあとパイナップル色の金かなと答えていたので、青を基調としたそのマンションと相乗効果になってよかったと思います。
シンガポールは「アジアのなかの赤い点」(red dot)と呼ばれているんです。地域的なことと、強権政治的なところを表現したものなのですけど、赤とブルーはコインの裏表として捉えることもできますよね。青はシンガポールの沈んだ悲しい部分を表現しているとも言える。つまりblue mansionは国そのものの比喩なんです。また、GDPの数字は高いし、きれいな国だけど、資源もない、という意味では国全体をマンションにたとえるのはいいなと思いました。
形式に関しても、この作品はフィルムノワールのジャンルに入りますので青が、音楽に関してはジャズが合うと思い、そうしました。
――俳優陣がとても魅力的だったのですが、監督はどのように演出されたのでしょうか?
この作品では多くの俳優が登場しますが、出演者の半分は過去20年間、演劇で私が共に仕事をしてきた人で、残りは私が知らないマレーシア人の俳優でした。ただ、共通しているのは全員演劇畑なんです。マレーシアもシンガポールも映画でキャリアを重ねる機会はなかなかないのですが、演劇のキャリアはみな豊富なので指示を与える必要はありませんでした。ですから、私のやり方は、愛情あふれた現場を作り、実験するように遠慮しないでやってもらうことでした。撮影現場というのは監督、スタッフ、俳優、それぞれにプレッシャーがかかりますから、そういう意味でも信頼と尊敬がいちばん大事だと思います。
――『青い館』は悲劇的な状況を描いていますが、コメディタッチであるところが面白いと思いました。
映画的な映画というものがあるとしたら、私の作品は演劇的なのかもしれません。ブレヒトが演劇でやる技法ですけど、人工的に描くほど、お客さんが鏡のように自分を反映させて、メッセージを受け取ってもらえると思っているんです。
――脚本家はどんな方なのでしょうか?
脚本のケン・クェックはケンブリッジで英文学を専攻し、シェイクピアの論文も書いた知識豊富な人です。ですから、『青い館』には、「ハムレット」や「リア王」のシェイクスピア作品や、ギリシャ悲劇の要素が入っているんです。人間の不条理な環境を反映したものというと黒澤明監督の映画に代表されると思いますが、私も人間がおかれる状況に興味があるので、そのテーマを取り込みました。
――撮影監督のラリー・スミスは『アイズワイドシャット』の方ですよね。スタッフは現代の国際的な映画界で活躍されている面々ですが、監督は彼らとは英語でコミュニケートし、キャストとはマレー語や中国語でやりとりするのですか?
撮影のラリー・スミスは『アイズ・ワイド・シャット』などを手掛けていますし、音楽のデイヴィッド・ヒルシュフェルダーは『シャイン』などの作曲者です。彼らとはいつも英語でコミュニケートします。シンガポールでは、私の世代は中華系の言葉を話さないんですよ。イギリス人化の教育があったので英語で教育を受けたんです。
――そうなると、当初から世界中の観客を想定して映画を作っているわけですね。
そうことは考えていないのですが、『青い館』についていえば、家父長制はアジアだけではなくイスラム教圏、キリスト経圏でも同じですから、あらゆる地域の人に理解してもらえるとは思っていますね。
――『フォーエバー・フィーバー』公開後、ミラマックスと企画に関する優先的な契約を結んでいましたが、その期間中に新作を作らなかったのはなぜでしょうか?
1988年から2003年までの5年間、ロンドンとニューヨーク、ロサンゼルスを往復しながら、企画開発をしていたのですが、納得いかなかったんです。つまり、彼らの望むものを作ろうとしていて、自分の作品ではなかった。それもあってシンガポールに帰りました。祖国に腰をすえて、商業的ではないものを作りたかったんです。
――次回作のアイデアはありますか?
舞台ですが、ケン・クェックと歴史ミュージカルを作ります。テーマは「愛はどこにあるのか」(笑)。ミュージカルはやったことないので挑戦したいと思っていて、ついに実現することになりました。映画では、『フォーエバーフィーバー』に出てきた女の子がまた登場してくるのですが、ロマンティックな小説を読んでいると人間の精神にどういうダメージを与えるか、という作品になると思います。でもコメディなんです(笑)。
聞き手 千浦僚