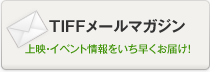2009.10.25
[インタビュー]
アジアの風部門『心の魔』:ホー・ユーハン監督インタビュー

僕は愛を知らない人々を描いているのです
『心の魔』

ホー・ユーハン監督
――『心の魔』は2つのことを描いています。1つは15歳の少女インと23歳の青年タッチャイとの社会的制裁を免れない恋愛。もう1つは貧富の差です。貧乏人と拝金主義の中流層は歩み寄れない。貧乏人に対して社会は無慈悲であるという冷酷な現実です。ホー監督は、実話をもとにした作品づくりが特徴ですが、この物語はどこまでが実話で、どこからがフィクションなのですか?
実話なのはあらすじだけです。裕福な男性と貧しい少女が付き合っていましたが、親に発覚してしまう。少女の両親はお金がほしいだけ。そこで問題が生じ、裁判になれば男性は刑を免れないので、怖れて少女を殺してしまったというのが実際にあった事件です。
映画の家族背景は僕がフィクションとして手を加えたものです。映画では男性の母親は雑貨店を営んでますが、現実には違います。また、少女の両親も中流家庭という設定にしてありますが、実際はそうではありません。会話や端々に登場するエピソードなどは創作です。
――母と子の設定は『RAIN DOGS』にも出てきましたよね。日本には母子ものというジャンルがありますが、この設定はホー監督の実体験に根ざしているのでしょうか。
そうではないんです。僕の両親は仲がよく、僕を愛してくれていて、いまも一緒に住んでいます(笑)。でも両親がそろっていない友達の家へ行くと、どこか寂しげです。その印象が自分のなかに残っていて、脚本を書くときに、無意識に出てくるんだと思います。
実際に少女を殺した青年には両親がいましたが、映画では母子家庭にしました。2つの家庭のコントラストを浮き彫りにして、父親不在でも強い絆がある母子を見せたかった。両親がいても幸せではない家庭もあるわけです。不完全でも強い愛はあると言いたくて、こういう設定にしました。
――映画に登場する15歳の少女は何も信じていません。愛を理解してないし、両親に対する反発心がありながらも、時と場合によっては、父親の存在を周到に利用する。何に対しても自由でありたいと望み、その自由をもてあましている思春期少女の存在を見事に描いています。
義務感や責任感という意識が育っていない彼女に、いま対処するには大きすぎる問題が急に降りかかってきてしまったわけです。つまり、彼女がしていることは「理由なき反抗」なんです。
――日本には少女マンガという、少女の心象風景や感情をすくいとる表現ジャンルがあります。監督は子供の頃、手塚治虫や白土三平、望月三起也など日本のマンガを読んでいたそうですが、少女マンガもお読みになりましたか?
いや、少年漫画しか読んだことがないんです(笑)。でも高校時代には、こういう感じの女の子がたくさんいました。彼女たちと付き合ったことはありませんが、将来の希望はあっても諦念も抱えていたりでバランスが悪かった。それがずっと印象に残っています。
――ホー監督も出演されたヤスミン・アフマド監督の『タレンタイム』を見て思ったことがあります。ヤスミン監督が人種間の壁を越えた人間の可能性を描いているとすれば、『心の魔』は人間をあえて限定的に描いている。人間はみな盲目的であり、めぐり合わせが悪ければ、最後のブザーを押してしまう存在ではないかというふうに。『タレンタイム』と『心の魔』は、その意味で相補的な関係にあるのではないでしょうか。
おっしゃるとおりですね。僕は『タレンタイム』がとても好きで、ヤスミンも『心の魔』を気に入ってくれたんです。2人で話し合ったんですが、ヤスミンの映画は愛がすべてを救うという観点で描かれ、僕の作品は愛がすべてを救うとは限らないと描いている。『心の魔』の登場人物は誰も愛を理解していない。知らないからどうすれば救えるのか、または救ってもらえるのかわからない。ヤスミンの映画に出てくる人たちはすでに愛を知っているけれど、僕の映画では混乱したまま事態が進展していくのです。
――『タレンタイム』のラスト近くで、主人公マヘシュとメルーが階段で手話のようなやりとりをします。もともとマヘシュは耳と口の不自由な少年という設定であり、映画ではマヘシュの手話に合わせて字幕が入りますが、この場面には字幕がありません。想像するしかない場面なのですが、ホー監督はどんな会話をしていると考えますか?
2人とも申し訳ないという気持ちがある一方で、やってしまったことを互いに認める気持ちもある。だから、いますぐには展開しないかもしれないけど、今後、何かあるかもしれないと思います。ただ一緒にいるのではなく、ああいう含みをもたせて2人の場面を終わらせるのはとてもいい。観客にこうなったらいいなと期待させるほうが効果的ですから。そういう余地を与えてくれる場面でした。
――『心の魔』を際立った作品にしているのは、1つは思春期少女の存在であり、もう1つは象徴性に富んだ後半の場面展開にあります。タッチャイはバイク事故を起こしたあと、夜のハイウェイに消えていきます。不在の家族の部屋に電話の着信音が鳴り響き、取調室に呼ばれた母親が不思議な笑みを見せる。そして夜の暗闇のなか、タッチャイが寝そべって月影を見ている。なぜ、このようなエンディングにしたのでしょう。タッチャイが背中を見せて消えていく場面では、クリント・イーストウッド監督の映画を思い出したのですが、イーストウッドはお好きですか?
すごく好きですね。『許されざる者』は大好きですし、そう言われてみると、『ミリオンダラー・ベイビー』も主人公が消えていくラストですね。じつは脚本では違っていたんです。タッチャイが工業地帯に隠れて、歩き回ったあと家に帰る、そこに警察が来る、というものだったんです。でも、逮捕劇にすると物語が完結してしまい、エモーショナルな広がりが出ないと思いました。また工業地帯で撮影していたら、アントニオーニとかツァイ・ミンリャン風になってしまうのでやめにしたんです。それで撮影監督に相談すると、バイク事故に遭わせたらどうだろうという話になった。僕もそのアイデアが気に入って、あのようなエンディングにしたわけです。むろん、タッチャイにも制裁がくだるべきですが、罰があると同時に赦しもある。両方の機会を与えたい気持ちがありました。
聞き手 赤塚成人