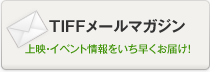2009.10.25
[インタビュー]
カルロス・レイガダス監督インタビュー


カルロス・レイガダス監督
――第22回東京国際映画祭 WORLD CINEMA部門で日本メキシコ友好400年記念としてカルロス・レイガダス監督の作品3本(『ハポン』、『バトル・イン・ヘブン』、『静かな光』)が今回初めてまとまった形で日本の観客に紹介されます。海外での高い評価は以前から耳にしていましたが、実際に作品が見られる機会は今までほとんどなかったので、とてもうれしく思います。
そこでまずお伺いしますが、監督の映画には論議を呼ぶような側面があると思います。つまり性的描写に関してですが、ご自身ではどのようにお考えですか?
セクシュアルなイメージが現れるのは、私の作品に必要なものだったからです。といっても、私がセクシュアルなイメージだけに特別な関心を持っているというわけではありません。しかしセクシュアルなイメージが作品そのものの重要な意味を伝えていたからこそ、私は作品の中にそうしたイメージを取り込んだのです。
――あなたの作品にセクシュアルなイメージが必要とされるのは、親密さと関係があるのではないでしょうか。
確かに親密さとも言えますが、それ以上のものです。映画は写真映像と関わりがあると私は考えています。つまり映画は写真映像に由来するものだということです。したがってそこには写真映像的真実(photographic truth)というものが存在します。映画の中で見、感覚するものは——もちろんある段階において、それが現実そのものではないことを私たちは脳によって判断していますが——現実だということです。私たちは現実生活におけるのと全く同様にその映像を知覚します。この原理の帰結として、映画製作とはそのような仕方で現実の人生を捉えるものだと言えます。実際にセックスをする時、私たちは大抵、裸です。それは生(life)の一部なのです。そして私はできるだけそこに近づこうとします。なぜなら私の考えでは、映画製作とは、機械仕掛けのようなドラマを作り出すものではなく、生を捉えるものであり、先ほど述べた写真映像的真実に関わるものだからです。
――監督の映画にはよく小さな子供が出てきますが、先ほど親密さという言葉を使ったのは、子供に向けられるキャメラに近しさを感じたからです。セクシュアルなものも同じ様に捉えているのではないでしょうか。セックスを特別なものとして描くのではなく、自然なものとして描いているところが素晴らしいと思います。
全く同感です。繰り返しになりますが、このことは生に関わりがあります。私たちにとって生との距離は時には遠く、時には近しいものです。例えば子供というのは生のすぐそばにいます。観客が私の映画を構築されたものとして眺めるのではなく、まさに現実生活のように感じてほしいと私は願っています。そして感情(feeling)や現実の生、例えば親密さといったものを捉えようと私は努力しているのです。
――3作品とも出演者は非職業俳優ですね。彼らへの演技指導はどのようにされているのでしょうか。
演技については、動きや台詞、振る舞いなど全て細かい点に到るまで指示しています。しかしそういう風には見えないでしょう。私にとって、映画のためのキャスティングはとても重要な要素なので、多くの労力と時間が費やされます。キャスティングが成功すれば、演技指導で悩む必要はありません。なぜなら彼らはそこにいて、言葉や振る舞いはそこから自然に生まれてくるからです。しかしキャスティングを失敗すると、全てが上手くいかなくなります。というのも私の映画のシステムは、多くの映画が採用している演劇的なシステムとは違うからです。大抵の映画では演技は一種の技術だと言えますが、私の映画はそのような技術を必要としません。
――キャストの存在感が素晴らしいと思います。
あなたがそう感じたことは私にとってとても重要です。なぜなら私は映画の中で、現実の生活と同様に、個々の人物を観客に感じてもらおうとしているからです。人物が放射しているものを活力(energy)という言葉で呼んでみましょう。もちろん活力は受け手の感情に左右される相対的なものです。しかし活力を放射する人物というものは、現実の生活におけるのと同様に、映画の中でも私たちに向けて活力を放射するのです。私の仕事は、演劇の演出家よりも肖像写真家によく似ています。私の考えでは、映画とは演劇よりも肖像写真に関わるものですから。
――今、写真という言葉が出ましたが、それはフランスの映画批評家アンドレ・バザンが写真映像について述べたことに近いのでしょうか。つまり現実の人物とその人の映像とが存在を分有するというか。
そうですね。
――非職業俳優を起用する映画作家というと、映画史上、何人か名前が挙がりますが、その中でも特にロベルト・ロッセリーニとロベール・ブレッソンが代表的です。しかしレイガダス監督の方法はその二人とも異なっています。例えば『バトル・イン・ヘブン』に主人公の運転手の妻の顔のクロースアップがありますが、その時、彼女の目が微妙に動いていますが、それは彼女が職業俳優ではないからです。監督の作品では、その人の持ち味がうまく活かされている感じを受けます。そうした方法が、監督の作品をドキュメンタリー的なものに近づけているのではないかと思います。
ブレッソンは特にこの方法を明確に理論化しましたが、彼は役柄を表現するために演技を用いる演劇に対し、個々人のリアリティに関わる映画(cinematograph)をはっきり区別しました。ブレッソンはあらゆる演劇的な演技や装置を廃します。彼の映画の登場人物の動きを固定することによって、そうした演劇的慣習を取り除くのです。しかし私が両者の違いを超えて発見したのは、彼のように演劇的慣習を廃すにしても、人物たちの活力を奪う必要はないということです。ブレッソンは俳優(actor)ではなくモデル(model)について語りました。しかし私の意見では、最終的にこのモデルはブレッソン自身の反映物、ほとんどゾンビのようなものと化してしまいます。彼の映画は常にパワフルですが、そこでは個々の人物は単なるモデルというものに縮小されています。あらゆるものを廃したとしても、人間の生というものだけは私は残しておきたいです。私の映画で人物が生き生きして見えるとしたら、私がその人の魅力を保存しようと努めているからです。
――その辺がレイガダス監督の映画がパワフルな印象を与える原因なのでしょうか。
うぬぼれるつもりは全くないのですが、私の映画に何かしら新しいところがあるとすれば、たぶん今述べた小さなことかも知れません。私の映画に出てくる非職業俳優を見て、以前見たことのある俳優とたいして変わりがないと思う人もいるでしょう。しかしあなたのように深い眼差しを持った観察者には、そこに固有な性質があることを感じ取ってもらえるはずです。
――非職業俳優を起用する映画作家の多くは、どうしてもブレッソンの模倣に陥りがちですが、その点、監督のやり方は非常にユニークだと思います。
非職業俳優を使う場合、逆のことも起こりえます。例えばブレッソンの対極にあるハリウッド映画のケースです。この場合、非職業俳優的な演技は全く機能しません。
――ショットについてお尋ねします。監督の作品ではショットの使い方がとてもユニークです。3作品に共通して360度のパンショットが出てくるですが、同一のショット内で、登場人物の主観的なイメージから客観的なイメージへ、またはその逆と、そのショットの位相が次々に変わっていくのが興味深いと思いました。
たぶんそうかも知れません。ただ意図的に、方法論的にそうしているわけではありません。映画は夢や想像といった内的な(internal)ヴィジョンの観念と結びついていると私は感じています。だからもし夢や催眠的なトランス状態で感じているものを映像によって視覚化するとしたら、その感情が主観的なのか客観的なのかをいちいち概念化する必要はありません。それは感情なのです。そして感情が映像化される時、時にカラーだったり、音がついていたり、あるいは全くそうしたものを欠いていたりします。このように私は映画を作っています。全てはじっくりと考えた結果というよりは、作っているうちにそうなるのです。
――いま「内的な」という言葉が出ましたが、人物の内面で何かが起こっていることを表現するために360度のパンショットが使われていたと思います。
そうですね。360度のパンショットはハッキリした例ですが、全てのキャメラ移動やフレーミングも内的なヴィジョンを表現する助けになっています。
――その場合のショット内の時間の流れ方が独特だと思います。ハリウッド的な映画製作では、基本的にあらゆるショットは物語に奉仕するようにできています。一方、レイガダス監督の映画では、人物が放心状態で何かを見つめている時が必ずあり、その眼差しの対象は小動物や天井から落ちる木の葉の動きだったりします。こうしたショットは物語的に何かを説明するわけではないのですが、とても印象に残ります。
あなたが、時間というものを速度ではなく、眼差しと関連づけて理解してくれたのは、とても嬉しいです。というのも問題は編集が速いとか遅いとかといったことではないからです。従来の多くの映画において、物語は概念的な仕方でのみ人生を再現してきました。つまりある概念が了解されたら、そこで立ち止まらずに次に進むというやり方です。例えばある人物が家を出て別の家に向かうことが示されたら、もう次のシーンではその場所に着いているというように。私にとっての問題は、この考え方のさらに先に進むことで、それは見ること、聴くことです。言うなれば、私は黙想=凝視(contemplation)を物語に対置します。概念を理解することより、現実世界を見ること、聴くことに関わる黙想という主題は、西欧の映画では今ではほとんど失われてしまったものです。日本映画ではどうかわかりませんが。
――日本映画も一緒だと思います(笑)。
(目の前にある日本製のキャンディーを見ながら)例えば小さな子供がキャンディーを見ているとしましょう。彼はその色や光の反射を見、実際に触って何か特別な感触を得るでしょう。これは何だろうと彼は考えます。そしてしばらく観察し、触って感じをつかもうとします。一方、私たち大人はそれがキャンディーであり、甘い味がするなどを知っています。その時、私たちは頭では理解していますが、きちんとそのものを見ようとはしません。木を例にとってみましょう。私たちは木を目にすると、木という言葉を思い浮かべ、プラトン的な意味において木の観念を頭の中で理解はしますが、それ以上、目の前にある木を観察しようとはしません。しかし生や映画は違います。それは見ることであり、聴くことです。
――先ほど「黙想=凝視」という言葉を使われましたが、監督の作品において重要なのは黙想=凝視の瞬間だと思います。現代の生活では効率性が重視されますから、黙想はそこから排除されてしまいます。しかし映画のルーツは写真映像であり、そこに流れる時間なので、黙想=凝視に着目されるのは、映画の本性にかなったものだと思います。
そうですね。黙想=凝視とは見る技術(art of looking)です。背後にあるドラマや物語の虜になるのではなく、単に見ることです。それによって物語以上のものを得ることができます。だから映画の中で黙想=凝視の時が大事なのです。なぜならそうした瞬間に魂(soul)が現れ出てくるからです。それは魂を「見る」ことのできる唯一の時です。先ほど物語以上のものと述べたのは、まさに魂のことです。物語だけにとらわれていると、魂を「見る」ことはできません。というのも物語とは目隠しのようなもので、現実に「ある」ものを覆い隠してしまうからです。私が非職業俳優を使うのも同じ理由からです。演技とは目隠しであり、その人物の人間性を隠してしまいます。
――『静かな光』の冒頭で、観客はそうした黙想=凝視の体験を共有するのではないでしょうか。あの長い夜明けのシーンです。
確かにその通りです。面白いことに、黙想=凝視からあまりにも遠く離れてしまったので、私たちは物事をきちんと見ることができず、そのため概念すらもはや役に立たず、間違ったりすることもあります。だから多くの人があの夜明けのシーンがリアルタイムで撮られたものなのか私に尋ねてくる始末です。実際の夜明けは数時間かかりますが、あのシーンは6分間しかありません。しかし多くの人があれをリアルタイムで撮られた夜明けだと勘違いしているのです。見ることからあまりに遠く離れてしまったために、概念すら間違ったものになってしまい、夜明けが6分間しかかからないと考えてしまうのです。
――時間といえば、監督の映画にはよく時計が出てきますね。画面外から聞こえてくる時計の音、あれは私たちの日常生活への言及なのでしょうか。
私は時間というものを無意識的なものだと解釈しています。つまり特定の反応を引き出す装置だとは考えていないということです。時間は本来、自然な生に属するものです。ところで私は時計が嫌いです。時計を見ると、時間が流れ出して行くような気分になります。時間を計るのも嫌いです。人生が逃げ去っていく、人生が終わりに向って進んでいる、そんな気分になるからです。人生があとどれだけ残っているのか勘定しているみたいです。こうした考えよりは、私はアフリカやメキシコの未開人の考えが好きです。彼らはあとどれだけ自分の人生が残っているかなどと考えたりしません。日本にも百歳以上の長寿の人がいると思いますが、こういう老人は自分がいつ生まれたとか、自分が何歳であるかなどそれほど正確には気にしないでしょう。私はこういう考えの方が好きです。時計の音を聞くと安心する人もいるかも知れません。なぜなら時計は本来触れることのできない時間というもの全てに管理の網を張って、彼らを慰めてくれるからです。しかし私は時間に網を張らない方を選びます。感情、自己自身、個人的な欲求、そして魂といったものは制御できないものです。その埋め合わせに私たちは全ての行動を時計に従って管理するという強迫観念に取りつかれているのです。一番わかりやすい例はアメリカの天気予報でしょう。馬鹿馬鹿しい位、細かく時間が設定されていて、何時に湿度がどうなるとか、何時に天気が変わるとかいう具合です。確かに平穏さや安心は得られるかも知れません。少なくとも二週間後の天気がわかるというわけです。でもそんなこと誰が気にかけるでしょう。ここ日本でも強迫観念によって分刻みに時間が管理されています。(映画祭のスケジュール表を見ながら)Q&Aを23時8分に開始したいので、22時48分に劇場に来て下さいだとか(一同笑)。私たちは自己自身からあまりにも遠く離れているので、その埋め合わせに時間を管理するという強迫観念に取りつかれているのです。
――だから監督は腕時計をされないのですね(笑)。
いや、そういうわけではありません(笑)。腕時計をしていた時期もありますが、その後、誰かにあげてしまい、していない時期もありました。2年間していたけど、その後、5年間はしていないとか。誰かと約束をするために時計が必要な時もありますが、今は必要ありません。ここ10年ほどは腕時計をしていません。
――私も腕時計をするのが嫌いなのですが(笑)。
(笑)。ただ時間を管理するという考え方を否定しているわけではありません。私が言いたいのは、そうした考え方の奴隷になってはいけないということです。もちろん時間を管理することは重要ですし、必要でもあります。農民には天気予報は必要なものですし、私たちの会見の時間も大事です。現代の生活についてアナーキーな考え方を提示しようとしているわけではないのです。
――『バトル・イン・ヘブン』の地下道のシーンで起きているのは、そうしたことだと思います。時計の耳障りな電子アラーム音が絶えず画面外から聞こえ、主人公の運転手を何かにせきたてているような印象を受けます。
それは現実にあることです。メキシコには露天商が沢山いて、3~40年前は伝統的な工芸品などを売っていたのですが、残念なことに今では時計等の中国製品に取って代わられてしまいました。40台もの時計のアラーム音を同時に聞きながら10時間も1人で商売をしている人の気分はどんなものなのだろうかと思います。
――逆に『静かな光』は、冒頭に柱時計の振り子が止まるシーンがあり、ラストで再び動き始めるという構成になっています。これは、普段見ている映画の時間とは異質の時間が今から流れ始めますよ、という宣言のように見えました。
これは、先ほど述べた魂に関する内的なヴィジョンを作り出すという観点からすると、興味深いシーンです。あなたが観察に基づいて、そう解釈しようとすることには同意します。確かにそう感じられるでしょう。それは夢を解釈するようなものです。しかし夢の解釈よりも、夢そのものの方がもっと重要なのです。泣きたくなるほど深い感情が訪れる時を想像してみましょう。そんな時、この作品のメノナイト派の人たちは時計を止めるのではないでしょうか。私が同じ立場だったら静けさを必要とするはずです。しかし明確な区分けをするためにそうしたわけではありません。主人公のヨハンは泣きたくなったから、静寂を欲したのです。彼はあの時、内面に集中しようとしたので、柱時計を止めたのです。脚本を書く時、私はそのシーンの内側に身を置いて感じるようにします。そしてその感情を映像化するのです。あなたが先ほど述べられたことは、あくまでも映画の物語を現実の世界から見た結果です。しかし私には、あのシーンに静寂が必要だと感じられたというのが本当のところです。強調しておきたいのですが、私がそう感じ、欲したということには合理的な理由があったわけではありません。そうした感情は前面に現れているものではなく、背後に隠されたものです。
――なるほど。こうしてお話を伺っていると、監督が感情を大事にされる方だということがわかりました。
私の方法は多くの映画作家の方法とは違っています。彼らは自動車の製造業者やコンピュータの設計者のように仕事をします。私はそんなことはしません。例えば、自然の生における創造といったことを考えてみましょう。自然を見てみればわかるように、そこにある全てのものには意味があります。夏の次には秋があり、花が咲いて種ができ、冬になって風が吹き、その風は種を散らして春を準備するといったように。もちろんこうした一連の出来事を計画し実行する、言うなれば一種の機械としての神のようなことを考える人はいるでしょう。この赤色やこの鳥やこの風を創造し、あるやり方で働かせる一種の機械としての神です。全ては導かれて=定められて(directed)います。少なくともこういう風に考えている人がいることは確かです。しかし私の考え方はこれとは別です。全ての出来事は別の理由によって起こります。全ては偶然によって生じますが、最終的にそれらは意味をなすのです。意味は確かに存在しますが、背後に隠れているもので、決して前面にあるものではありません。物事は何かの指示(direction)に従って生じるのはなく、単に起きるのであり、後から意味をなすのです。背後にある意味と無意味は全てものを二重にし、パワフルにします。可視と不可視のものについて語るキリスト教神学や他の全ての宗教が用語法において矛盾していると私は考えるのはそのためです。こうした二重性や共存在性、つまり一方に善があり他方に悪があるのではなく、全てはそれらを同時に含んでいて、しかも生き生きとしている。これが生というものだと思います。
――『静かな光』を見ると、どうしてもデンマークの偉大な映画作家カール・ドライヤーの名前が思い浮かんでしまいます。ドライヤーの映画にも、いま、ここにあるものを肯定するという面があると思います。監督はドライヤーに親近感を抱いているのではないかと想像しますが、それは今述べられたような理由からなのでしょうか。
確かに私はカール・ドライヤーの映画、それも特に『奇跡』が大好きです。あの映画ではまさに私の映画と同様のことが起こります。しかしドライヤーの映画は奇跡に関するもので、全てはこの主題をめぐって構築されています。劇的な仕方で奇跡を起こすために、あの映画は作られています。奇跡が起こるのは神の介入によってです。しかし私の映画はこれとは全く違っています。あの女性が甦るのは、彼女がいなくなってしまうのはあまりに悲しいと私が感じたからです。しかしドライヤーの映画においては、神の存在証明のためにそれが行われます。2つの映画の間には無限の隔たりがあります。地方のプロテスタントの家族の中で女性を生き返らせるという点において互いに類似していますが、あくまで表面上のものです。
――ドライヤーの『奇跡』ではキリストの生まれ変わりのような男の言葉によって死んだ女が甦りますが、『静かな光』では敵対していたはずの女のくちづけによって甦るところが決定的に違いますね。
その通りです。映画好きの方は深遠にみえるものに惹かれがちなので、多くの人がドライヤーについて尋ねるのですが、ウォルト・ディズニーについては誰も私に尋ねません。ご指摘のように彼女はくちづけによって目覚めます。誰もウォルト・ディズニーについて尋ねないのは、それが浅薄な考えに思えるからです。あのディズニーのヒロインが目覚めたのは、くちづけをしたのが美しい王子だったからで、彼が美しくなかったら結果は違っていたでしょう(笑)。私の映画の最後にあるのは、ディズニー的な要素、つまり愛、人間的な愛という考えです。あの女性のくちづけによって彼女が甦るのを私たちは目にするわけですが、彼女を甦らせたのは人間的な愛なのです。しかしディズニーの映画同様、彼女自身に何らかの力が備わっているわけではありません。
――じつは私もあのシーンを見て『眠れる森の美女』を連想したのですが、それを尋ねるのは失礼かと思い、黙っていました(笑)。
そう言われたほうがうれしかったかもしれません(笑)。
今日は感情について話してきました。というのも私が映画を作るのは感情を表現するためだからです。感情とは生についての考えです。そしてそれは映画と結びついています。映画作家というものは、どうやって映画を作るかではなく、この感情をどうやったら他の人と共有できるかを考えているのだと私は思います。
――ひとことで言うと魂の問題ということですね。
魂と思索です。あえて言うなら魂についての思索です。私は魂と思索を信じているのです。

インタビュー・構成 葛生賢(くずう さとし)