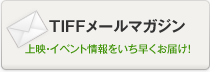2009.10.20
[イベントレポート]
怪奇幻想映画の旗手を語る! 『怪奇猿男』+『麻瘋女』:10/19(月)トークショー
10月19日にシネマート六本木で上映された、マーシュイ・ウェイパン(馬徐維邦)監督の2作品『怪奇猿男』と『麻瘋女』。
この2本、『怪奇猿男』はサイレントの18コマ/秒、『麻瘋女』はトーキーの24コマ/秒という上映方式のため、映写機のセッティングを変更する必要があり、その時間を利用してのトークショーが開催されました。
登壇されたのは、徹底的なリサーチに裏づけされた著作の数々で、アジア映画ファンからの人気も高い、映画研究家の劉文兵さんと、アジアの風部門の石坂健治プログラミング・ディレクター(以下、PD)。

先に上映された『怪奇猿男』で、「オイシイところをさらっていく」探偵役を演じているのがマーシュイ監督その人であるというミニ・エピソードを枕に、トークは劉さんによる「監督の経歴紹介」からスタート。
「1901年に生まれたマーシュイ監督の、元々の姓は“シュイ”(徐)。その後、馬家に婿入りしたため、2つの姓をあわせてマーシュイを名乗るようになりました。1923年に上海で映画界入りしたマーシュイ監督は、当初は美術スタッフ兼俳優としてキャリアをスタートするものの、1926年に監督デビュー。今回上映された『怪奇猿男』は、監督第3作目にあたります」
後年、中国・怪奇幻想映画の第1人者と呼ばれるようになるマーシュイ監督の代表作といえば、1937年に製作された『夜半の歌声』。同作は、1995年に『夜半歌聲/逢いたくて、逢えなくて』のタイトルで、レスリー・チャン(張國榮)主演作としてリメイクされるほどの作品ですが、劉さんの研究によれば、1931年にはじまった国民党政府の映画検閲制度と、満州事変が映画界に与えた影響は大きく、東洋の娯楽映画発信基地であった上海も、左翼映画、抗日映画の気運が高まり、そこにトーキー化の波が重なって、マーシュイ監督を含めた作り手たちの作風が変わっていったとのこと。
『怪奇猿男』は、その直前の1930年の作品、『麻瘋女』は1939年の作品ですから、そういった時代背景に思いを馳せながら作品を楽しむというのも、なかなか興味深い体験だったのではないでしょうか。

戦後は活動の場を香港へと移したマーシュイ監督ですが、低予算&早撮りが基本の香港では、「じっくり時間をかけて作品を仕上げる」マーシュイ・スタイルが受け入れられることはなく、中国映画史では、「香港時代のマーシュイ・ウェイパンは凡作を量産していた」こととなっています。ですが、石坂PDは未だ見ぬ「マーシュイ・ウェイパンの香港映画」に興味津々。北京や香港のフィルムアーカイブにも保管されていない、それらの作品を探し出すことは困難な作業ですが、「映画コレクターの個人所有や、台湾方面に現存するかも」との情報もあるようですので、もしかすると数年後の東京国際映画祭で上映!ということがあるかもしれません。

この他にも、マーシュイ監督の「異形のものをフィーチャーする」独特の作風は、幼少期の不幸な体験が影響しているのでは?という劉さんの考察や、『麻瘋女』主演女優のタン・イン(談瑛)の「強烈なアイ・メイク」にまつわるエピソード、石坂PDによる東南アジア弁士事情紹介など、話題は多岐に及んだのですが、残念ながらのタイムアップ。約10分間の休憩をはさんで、『麻瘋女』の上映が始まったのでした。
この2本、『怪奇猿男』はサイレントの18コマ/秒、『麻瘋女』はトーキーの24コマ/秒という上映方式のため、映写機のセッティングを変更する必要があり、その時間を利用してのトークショーが開催されました。
登壇されたのは、徹底的なリサーチに裏づけされた著作の数々で、アジア映画ファンからの人気も高い、映画研究家の劉文兵さんと、アジアの風部門の石坂健治プログラミング・ディレクター(以下、PD)。

映画研究家の劉文兵さん
先に上映された『怪奇猿男』で、「オイシイところをさらっていく」探偵役を演じているのがマーシュイ監督その人であるというミニ・エピソードを枕に、トークは劉さんによる「監督の経歴紹介」からスタート。
「1901年に生まれたマーシュイ監督の、元々の姓は“シュイ”(徐)。その後、馬家に婿入りしたため、2つの姓をあわせてマーシュイを名乗るようになりました。1923年に上海で映画界入りしたマーシュイ監督は、当初は美術スタッフ兼俳優としてキャリアをスタートするものの、1926年に監督デビュー。今回上映された『怪奇猿男』は、監督第3作目にあたります」
後年、中国・怪奇幻想映画の第1人者と呼ばれるようになるマーシュイ監督の代表作といえば、1937年に製作された『夜半の歌声』。同作は、1995年に『夜半歌聲/逢いたくて、逢えなくて』のタイトルで、レスリー・チャン(張國榮)主演作としてリメイクされるほどの作品ですが、劉さんの研究によれば、1931年にはじまった国民党政府の映画検閲制度と、満州事変が映画界に与えた影響は大きく、東洋の娯楽映画発信基地であった上海も、左翼映画、抗日映画の気運が高まり、そこにトーキー化の波が重なって、マーシュイ監督を含めた作り手たちの作風が変わっていったとのこと。
『怪奇猿男』は、その直前の1930年の作品、『麻瘋女』は1939年の作品ですから、そういった時代背景に思いを馳せながら作品を楽しむというのも、なかなか興味深い体験だったのではないでしょうか。

左は石坂健治プログラミング・ディレクター
戦後は活動の場を香港へと移したマーシュイ監督ですが、低予算&早撮りが基本の香港では、「じっくり時間をかけて作品を仕上げる」マーシュイ・スタイルが受け入れられることはなく、中国映画史では、「香港時代のマーシュイ・ウェイパンは凡作を量産していた」こととなっています。ですが、石坂PDは未だ見ぬ「マーシュイ・ウェイパンの香港映画」に興味津々。北京や香港のフィルムアーカイブにも保管されていない、それらの作品を探し出すことは困難な作業ですが、「映画コレクターの個人所有や、台湾方面に現存するかも」との情報もあるようですので、もしかすると数年後の東京国際映画祭で上映!ということがあるかもしれません。

『麻瘋女』のタン・インの独特のアイメイク
この他にも、マーシュイ監督の「異形のものをフィーチャーする」独特の作風は、幼少期の不幸な体験が影響しているのでは?という劉さんの考察や、『麻瘋女』主演女優のタン・イン(談瑛)の「強烈なアイ・メイク」にまつわるエピソード、石坂PDによる東南アジア弁士事情紹介など、話題は多岐に及んだのですが、残念ながらのタイムアップ。約10分間の休憩をはさんで、『麻瘋女』の上映が始まったのでした。